Memo
カテゴリ「小説」に属する投稿[9件]
友達とのお題書き合いで、モブ×レンマサを書きました。モブの集団にレンマサ(付き合っている)が犯される話です。当然ながらR18です。
……喧しい。
真斗は目を閉じたまま、深く息を吐いた。拍手喝采が鳴り響いて止まない。いつもならそれは彼にとって喜ばしいものである筈なのに、今聞こえてくる響きはただ耳障りなものでしかなかった。瞼が重くて開かない。真斗はなんとかしてもう一度眠ろうとした。
「聖川っ!」
その瞬間、聞こえてきた叫び声に真斗はすぐさま正気に返った。そして、彼は自分が置かれている異常な状況に気づいた。
「……これは」
「良かった。大丈夫か?」
目の前には両手足を拘束されたレンが首だけを動かして真斗の顔を覗き込んでいた。暴れたのか、手首には既に血が滲んでいる。咄嗟に駆け寄ろうとして、真斗は自分も拘束されていることに気づいた。
周囲を見渡すとスポットライトがこちらへと向けられているのが見える。レンと真斗は舞台の上で拘束されているらしかった。小さな会場は満員のようだったが、向けられる光が強すぎて、席にいる大半が男だということしか分からなかった。
「神宮寺、なんだこれは。どういうことだ」
「それが分かったら苦労しないさ」
そう吐き捨てると、レンは観客席の男達を睨み付けた。だが、まるでファンサービスでも向けられたような歓声が返ってくるばかりで何の情報も得られない。
「ドッキリ……にしては質が悪い」
「誘拐か」
「多分ね」
二人が話が出来たのはそこまでだった。ファンファーレが響き、豚の被り物をしてスーツを着た男が舞台上に現れた。男は二人の側を素通りすると、観客に向かって呼びかけた。
「皆様、ようこそいらっしゃいました! 本日お見せするのは尊い愛の物語です。きっとご満足いただけるでしょう」
観客達は足を踏みならして口笛を吹き、思い思いに騒いでいる。まるでB級ホラー映画のような情景に真斗が声も出せずにいると、男に向かって神宮寺が叫んだ。
「おい! 事務所も通さずにこんなショーに呼び出して、一体何が目的だ?」
男はレンの呼びかけには答えず、首だけをレンの方へと向けた。
「身代金目当てだろうけど、今のうちにオレたちを解放した方が……」
レンの言葉を待たずに、男はつかつかと真斗の方へ歩み寄る。その頬を男は強く打った。
「……!?」
「っ……!? ねぇ、今話してるのはオレの方なんだけど」
目を見開く二人を無視して、男は真斗の髪を掴んだ。
「くっ……!」
「おいやめっ!」
レンが止める前に男は真斗へ拳を振り下ろした。髪を掴まれて逃れられず、真斗の唇が切れて血が流れる。
「…………っ」
目を伏せてレンが口を閉じると、男は満足げに頷いた。彼が乱暴に手を放すと、少し乱れた真斗の髪が揺れる。観客席からは驚きが含まれたどよめきに満ちた。
「いいねぇ、高い金を払っただけはある」
「噂は本当だったな」
「御曹司同士でなんて、一世一代のロマンスじゃないか。ねぇ?」
その時、二人はここにいる人間がどういう類いか理解し始めていた。そしてこれから何が始まるかも予想出来てしまった。男は鋏を懐から取り出すと、しょきしょきと音を立てながら真斗に近づいていく。
「好きにするがいい。……代わりに神宮寺だけは手を出さないで欲しい」
真斗は男から目を逸らさず、観客を喜ばせないよう淡々と願いを述べた。男は自身の顎に軽く手を当てて頷いた。
「簡単なインタビューに答えるなら考えてもいいですよ」
「分かった」
「聖川は黙ってろ! こんな連中がそんな話に乗るわけないだろ!」
「黙っているべきなのは貴方です」
男が鋏の刃を軽く真斗の首に当てると、レンは歯を食い縛りながら口を閉ざした。男はそのまま上機嫌に真斗の服を鋏で切り開いていく。その間、真斗は男からの質問に答えた。
名前、身長、体重など答え慣れたものから、普段の自慰の回数や性感帯、そしてレンとの関係に踏み込んだ悪趣味なものまで、真斗は所々で息を詰まらせながらも答えていく。真斗が答える度に観客はゲラゲラと下品な笑い声を垂れ流した。その情景をレンは見ていることしか出来なかった。だが、思わず止めようと叫びそうになる度に、真斗はレンへと視線を向ける。その真剣な眼差しに込められた意図など分かっていた。レンは必死に口を閉ざし続けた。
鋏が下着にまで入った時、思わず真斗は恐怖で身を固くする。その様を男は煽り立て、粗雑に下着は切り裂かれた。何人もの観客の目が真斗の肌を這っていく。頬は羞恥で染まり、伏せられた睫が影を落とした。男は真斗の腿を掴むと、背後から抱え上げる。衆人環境に恥部が晒され、観客達は歓声を上げた。
「これは相当可愛がられているな」
「純情そうな顔をして、一皮剥けばこれか」
「クソッ、マジで貫通済みかよ」
「ギチ膣よか慣れてる方がずっといいさ」
観客のざわめきが響く中で、男は真斗の腿にも拘束具を付け、足を開かせたままにした。真斗は最早顔を上げられず、深く俯く。男はすぐに真斗の髪を掴むと、観客達へと顔を向けさせた。潤んだ瞳がライトの輝きを反射する。頬には涙が伝い、耳まで赤く染まっているのがレンからはっきりと見えた。
もう耐えられそうにない。レンが大声で叫ぼうとした瞬間、ベルトが引き抜かれた。レンの背後に誰かいる。荒い息が首にかかり、背後から強く抱きしめられた。そのままスラックスが下ろされ、レンが声を出す前に指が内部に入り込んだ。
「あ゛ぁ……っ!」
「ふふっやっぱりレンちゃんは処女だったねぇ……」
背後の男はそう言うと、レンの後孔に指を出し入れし、強引に拡張をし始める。これまで感じたことのない痛みに、レンは必死に声を抑えようとしたが漏れ出る呻き声は止められなかった。
「レンッ! 貴様ら……約束が違う!」
「そういえば普段の呼び方は聞いてませんでしたね。名前で呼んでるんですねぇ」
事態に気づいた真斗が男に吠えたが、男も観客達も愉悦に浸りながら笑うばかりだった。「なんと愛らしい」
「見ましたか? あの鬼神のような顔。壮絶な美しさ……」
「必死に堪えるレン君も可愛かったですねぇ。心配をかけまいとして」
真斗は怒りのままに体を暴れさせたが、自由な腰が動くばかりで男達の目を楽しませる結果にしかならなかった。
「いい加減にしろ、この卑怯者……っ!?」
叫ぶ真斗も男達の手から逃れることは出来なかった。ローションに塗れた指が内部に入り込み、真斗は恐怖から身を固くする。だが、それを見越していたかのように舞台には観客が上がっていき、真斗の全身に手を這わせた。口内を撫でられ、乳首に爪が立てられる。脇を擽り、陰茎を何度も強く擦られた。行為に慣れた体は瞬く間に快楽を拾い、真斗の怒号が歪んでいく。
「やめっ……まさ、とっ!」
「いや、ら……れん……」
男が観客に呼びかけ、舞台に上がる人間は増えていく。拘束はいつの間にか外されていたが、この圧倒的な人数差の前で自由など無い。
「う゛あぁあ゛っ!」
レンの内部に陰茎が深く入り込み、歓声が沸き起こる。
「嫌だっ! やめろっ……ぐっ……ぁ……!」
愛撫に耐えきれず、真斗は白濁を散らす。
そのまま二人は互いの姿を見せされながら犯された。体液を舐められ、内部を暴かれる度に、苦痛、怒りそして悲しみだけが二人の心に満ちていく。レンの脚には強引に挿入されて切れた血が流れ、腐臭を吐く男に真斗は唇を奪われた。嫌だと幾ら喚いても、せめて相手は助けてほしいと願っても、返ってきたのは歓声と拍手だけだった。
何時間も経った頃、既に半ば正気を失ったレンと真斗は男達に体を揺さぶられているだけだった。男はレンと真斗の髪を掴むと、二人の唇を強引に合わせる。
「レン……?」
「ま、さと……?」
二人は僅かに意識を取り戻し、互いを求める心のままに口づけを交わした。白濁と血が混じった唾液が垂れる。会場が揺れるほどの拍手が巻き起こり、感動の涙を流す者もいた。
「すま……ない……」
「ごめん……」
だが、二人の心を占めているのは相手の姿だけだった。周囲の喧噪など、何一つ意味は無い。舞台にいるのは彼等だけだった。畳む
……喧しい。
真斗は目を閉じたまま、深く息を吐いた。拍手喝采が鳴り響いて止まない。いつもならそれは彼にとって喜ばしいものである筈なのに、今聞こえてくる響きはただ耳障りなものでしかなかった。瞼が重くて開かない。真斗はなんとかしてもう一度眠ろうとした。
「聖川っ!」
その瞬間、聞こえてきた叫び声に真斗はすぐさま正気に返った。そして、彼は自分が置かれている異常な状況に気づいた。
「……これは」
「良かった。大丈夫か?」
目の前には両手足を拘束されたレンが首だけを動かして真斗の顔を覗き込んでいた。暴れたのか、手首には既に血が滲んでいる。咄嗟に駆け寄ろうとして、真斗は自分も拘束されていることに気づいた。
周囲を見渡すとスポットライトがこちらへと向けられているのが見える。レンと真斗は舞台の上で拘束されているらしかった。小さな会場は満員のようだったが、向けられる光が強すぎて、席にいる大半が男だということしか分からなかった。
「神宮寺、なんだこれは。どういうことだ」
「それが分かったら苦労しないさ」
そう吐き捨てると、レンは観客席の男達を睨み付けた。だが、まるでファンサービスでも向けられたような歓声が返ってくるばかりで何の情報も得られない。
「ドッキリ……にしては質が悪い」
「誘拐か」
「多分ね」
二人が話が出来たのはそこまでだった。ファンファーレが響き、豚の被り物をしてスーツを着た男が舞台上に現れた。男は二人の側を素通りすると、観客に向かって呼びかけた。
「皆様、ようこそいらっしゃいました! 本日お見せするのは尊い愛の物語です。きっとご満足いただけるでしょう」
観客達は足を踏みならして口笛を吹き、思い思いに騒いでいる。まるでB級ホラー映画のような情景に真斗が声も出せずにいると、男に向かって神宮寺が叫んだ。
「おい! 事務所も通さずにこんなショーに呼び出して、一体何が目的だ?」
男はレンの呼びかけには答えず、首だけをレンの方へと向けた。
「身代金目当てだろうけど、今のうちにオレたちを解放した方が……」
レンの言葉を待たずに、男はつかつかと真斗の方へ歩み寄る。その頬を男は強く打った。
「……!?」
「っ……!? ねぇ、今話してるのはオレの方なんだけど」
目を見開く二人を無視して、男は真斗の髪を掴んだ。
「くっ……!」
「おいやめっ!」
レンが止める前に男は真斗へ拳を振り下ろした。髪を掴まれて逃れられず、真斗の唇が切れて血が流れる。
「…………っ」
目を伏せてレンが口を閉じると、男は満足げに頷いた。彼が乱暴に手を放すと、少し乱れた真斗の髪が揺れる。観客席からは驚きが含まれたどよめきに満ちた。
「いいねぇ、高い金を払っただけはある」
「噂は本当だったな」
「御曹司同士でなんて、一世一代のロマンスじゃないか。ねぇ?」
その時、二人はここにいる人間がどういう類いか理解し始めていた。そしてこれから何が始まるかも予想出来てしまった。男は鋏を懐から取り出すと、しょきしょきと音を立てながら真斗に近づいていく。
「好きにするがいい。……代わりに神宮寺だけは手を出さないで欲しい」
真斗は男から目を逸らさず、観客を喜ばせないよう淡々と願いを述べた。男は自身の顎に軽く手を当てて頷いた。
「簡単なインタビューに答えるなら考えてもいいですよ」
「分かった」
「聖川は黙ってろ! こんな連中がそんな話に乗るわけないだろ!」
「黙っているべきなのは貴方です」
男が鋏の刃を軽く真斗の首に当てると、レンは歯を食い縛りながら口を閉ざした。男はそのまま上機嫌に真斗の服を鋏で切り開いていく。その間、真斗は男からの質問に答えた。
名前、身長、体重など答え慣れたものから、普段の自慰の回数や性感帯、そしてレンとの関係に踏み込んだ悪趣味なものまで、真斗は所々で息を詰まらせながらも答えていく。真斗が答える度に観客はゲラゲラと下品な笑い声を垂れ流した。その情景をレンは見ていることしか出来なかった。だが、思わず止めようと叫びそうになる度に、真斗はレンへと視線を向ける。その真剣な眼差しに込められた意図など分かっていた。レンは必死に口を閉ざし続けた。
鋏が下着にまで入った時、思わず真斗は恐怖で身を固くする。その様を男は煽り立て、粗雑に下着は切り裂かれた。何人もの観客の目が真斗の肌を這っていく。頬は羞恥で染まり、伏せられた睫が影を落とした。男は真斗の腿を掴むと、背後から抱え上げる。衆人環境に恥部が晒され、観客達は歓声を上げた。
「これは相当可愛がられているな」
「純情そうな顔をして、一皮剥けばこれか」
「クソッ、マジで貫通済みかよ」
「ギチ膣よか慣れてる方がずっといいさ」
観客のざわめきが響く中で、男は真斗の腿にも拘束具を付け、足を開かせたままにした。真斗は最早顔を上げられず、深く俯く。男はすぐに真斗の髪を掴むと、観客達へと顔を向けさせた。潤んだ瞳がライトの輝きを反射する。頬には涙が伝い、耳まで赤く染まっているのがレンからはっきりと見えた。
もう耐えられそうにない。レンが大声で叫ぼうとした瞬間、ベルトが引き抜かれた。レンの背後に誰かいる。荒い息が首にかかり、背後から強く抱きしめられた。そのままスラックスが下ろされ、レンが声を出す前に指が内部に入り込んだ。
「あ゛ぁ……っ!」
「ふふっやっぱりレンちゃんは処女だったねぇ……」
背後の男はそう言うと、レンの後孔に指を出し入れし、強引に拡張をし始める。これまで感じたことのない痛みに、レンは必死に声を抑えようとしたが漏れ出る呻き声は止められなかった。
「レンッ! 貴様ら……約束が違う!」
「そういえば普段の呼び方は聞いてませんでしたね。名前で呼んでるんですねぇ」
事態に気づいた真斗が男に吠えたが、男も観客達も愉悦に浸りながら笑うばかりだった。「なんと愛らしい」
「見ましたか? あの鬼神のような顔。壮絶な美しさ……」
「必死に堪えるレン君も可愛かったですねぇ。心配をかけまいとして」
真斗は怒りのままに体を暴れさせたが、自由な腰が動くばかりで男達の目を楽しませる結果にしかならなかった。
「いい加減にしろ、この卑怯者……っ!?」
叫ぶ真斗も男達の手から逃れることは出来なかった。ローションに塗れた指が内部に入り込み、真斗は恐怖から身を固くする。だが、それを見越していたかのように舞台には観客が上がっていき、真斗の全身に手を這わせた。口内を撫でられ、乳首に爪が立てられる。脇を擽り、陰茎を何度も強く擦られた。行為に慣れた体は瞬く間に快楽を拾い、真斗の怒号が歪んでいく。
「やめっ……まさ、とっ!」
「いや、ら……れん……」
男が観客に呼びかけ、舞台に上がる人間は増えていく。拘束はいつの間にか外されていたが、この圧倒的な人数差の前で自由など無い。
「う゛あぁあ゛っ!」
レンの内部に陰茎が深く入り込み、歓声が沸き起こる。
「嫌だっ! やめろっ……ぐっ……ぁ……!」
愛撫に耐えきれず、真斗は白濁を散らす。
そのまま二人は互いの姿を見せされながら犯された。体液を舐められ、内部を暴かれる度に、苦痛、怒りそして悲しみだけが二人の心に満ちていく。レンの脚には強引に挿入されて切れた血が流れ、腐臭を吐く男に真斗は唇を奪われた。嫌だと幾ら喚いても、せめて相手は助けてほしいと願っても、返ってきたのは歓声と拍手だけだった。
何時間も経った頃、既に半ば正気を失ったレンと真斗は男達に体を揺さぶられているだけだった。男はレンと真斗の髪を掴むと、二人の唇を強引に合わせる。
「レン……?」
「ま、さと……?」
二人は僅かに意識を取り戻し、互いを求める心のままに口づけを交わした。白濁と血が混じった唾液が垂れる。会場が揺れるほどの拍手が巻き起こり、感動の涙を流す者もいた。
「すま……ない……」
「ごめん……」
だが、二人の心を占めているのは相手の姿だけだった。周囲の喧噪など、何一つ意味は無い。舞台にいるのは彼等だけだった。畳む
モブセシ習作。
メスイキすると自律神経がイカれて寂しがりやになり、故郷を懐かしむような気持ちになるというネット豆知識から。
「ねぇ、懐かしい?」
「は……?」
セシルの問いが聞こえていないのか、男はセシルの首筋に顔を埋めながら、より強い力で乳首を摘んだ。
「い゛っ!」
「気持ち良過ぎるとねぇ、神経がおかしくなっちゃって涙が止まらなくなって、寂しい気持ちになっちゃうんだって」
男は弄る手を止めずにそんなことをボソボソと話し続ける。
だが、セシルが今感じているのは、そんな甘い快楽ではなく恐怖と鈍い痛みだけだった。
「っ……もうやめてください」
「セシル君、寂しがりだもんね。ずっと弄られたらさみしくなっちゃうだろうし、僕がずっと側にいるからね」
男はセシルの頬に優しく口付ける。
確かにセシルは孤独を感じていた。だが、それは男が思うような甘いものではなく、この部屋に自分の心を解する者がいないという絶望にも似た確信だった。畳む
メスイキすると自律神経がイカれて寂しがりやになり、故郷を懐かしむような気持ちになるというネット豆知識から。
「ねぇ、懐かしい?」
「は……?」
セシルの問いが聞こえていないのか、男はセシルの首筋に顔を埋めながら、より強い力で乳首を摘んだ。
「い゛っ!」
「気持ち良過ぎるとねぇ、神経がおかしくなっちゃって涙が止まらなくなって、寂しい気持ちになっちゃうんだって」
男は弄る手を止めずにそんなことをボソボソと話し続ける。
だが、セシルが今感じているのは、そんな甘い快楽ではなく恐怖と鈍い痛みだけだった。
「っ……もうやめてください」
「セシル君、寂しがりだもんね。ずっと弄られたらさみしくなっちゃうだろうし、僕がずっと側にいるからね」
男はセシルの頬に優しく口付ける。
確かにセシルは孤独を感じていた。だが、それは男が思うような甘いものではなく、この部屋に自分の心を解する者がいないという絶望にも似た確信だった。畳む
捧げ物として書いたR18のモブレンを公開しておきます。なんでも許せる方向け。
蓮華ちゃんはこの世の奇跡だった。
あれはまだ俺が社会に出たばかりの時だった。当時、今でいうブラック企業でこき使われていた俺は、生きる希望を失っていた。
もう死のう。営業回りで怒鳴りつけられた帰り道で、俺は薄暗い決意をした。その時だった。街頭テレビから歌声が降り注いだのは。映っていたのはまだ売り出し中だった神宮寺蓮華だった。
圧倒的な技術と美しい声で紡がれる歌は、俺を此処ではない楽園へと連れて行った。目を引いて離さない美貌とオーラも堪らなかった。霞む視界の中で、食い入るようにテレビを見つめていた。
それから俺は蓮華ちゃんと虜になった。CDを買って毎日曲を聴いて、ライブに行って、彼女に勇気づけられたから俺は仕事にも打ち込むことが出来た。蓮華ちゃんは俺の恩人だった。
だから頑張って耐えた。毎日の理不尽な仕事にも、蓮華ちゃんが明らかに金目当ての年の差婚をしても、彼女が引退してしまっても。俺はずっと蓮華ちゃんを忘れずにいた。彼女が存在しているだけでこの世界を俺は愛おしいと思えた。
それでも、いや、だからこそ蓮華ちゃんがこの世から消えてしまうことには耐えられなかった。
その報道を聞いた時、世界が終わったと思った。その時、俺は会社でもある程度の地位に上り詰めていたが、そんなことはどうでも良くなった。蓮華ちゃんがいない世界に意味はない。後はもうくだらない消化試合だ。抜け殻になった俺は十数年を無為に過ごした。蓮華ちゃん以上に愛せる存在も見当たらなくて、結婚もしていない。家族や親戚なんかもとうに死んだ。これから寿命が尽きるまで生き続けるのだと思うと耐えがたかった。
もう死のう。仕事をしながらそう決意した日、俺は会社がスポンサーをやっている関係で番組制作の内見があった。蓮華ちゃんが生きていた世界を覗けるかもしれない。人生最後の仕事にはふさわしい。そう思って俺は現場に出かけた。
見学する番組は話題の歌手が生放送で歌ってトークをするのが売りの音楽ショーだった。
蓮華ちゃんが亡くなってからテレビなんて一切見なかったから、そこにいる芸能人を俺は誰一人知らなかった。女性アイドルグループが金切り声で歌うのを聞きながら、俺は少し憂いを含んだ蓮華ちゃんの歌声を思い出していた。やっぱりもう蓮華ちゃんはいないんだ。そう思わされるのが辛かった。
もう結構です、そう言って切り上げようとしたその時、ステージに立った人がいた。
彼女そっくりの明るい髪が揺れて、真っ青な瞳が俺を映した。蓮華ちゃん――そう叫びかけて、違うと気づいた。
すらりと高い背、低い声、ステージにいるのは男だった。俺が動揺している間に、前奏が流れて彼は歌い始めた。その歌声ではっきりと分かった。圧倒的な技術と誰もが目を離せないオーラ、同じだった。性別は違っても蓮華ちゃんはまた俺を救いに来てくれたんだ。
そう思えて涙が止まらなかった。会場の大歓声から神宮寺レンって聞こえてくる。
蓮華ちゃんの息子だと知ったのはその後だった。蓮華ちゃんはまだレン君の中で生きているんだ。そしてあの時みたいに俺を救いに来てくれたんだ。俺は確信を持ってその事実を噛みしめていた。
番組への予算を増やすから、レン君と話したい。そうスタッフに声を掛けるとすぐにお膳立てしてもらえた。俺が偉いからこういうことも言える。仕事に打ち込み続けたことが無駄じゃなかったって初めて思えた。
レン君と取る夕食は夢のようだった。俺は全く知らなかったけど、レン君はかなりの売れっ子らしい。今日の収録の裏話や、音楽へのこだわりを軽快に喋ってくれてとても楽しかったし、なにより見れば見るほど蓮華ちゃんに似ていた。雰囲気もそうだし、歌い方も、華やかさも、なにもかも生き写しだった。
それからは全く同じだった。レン君のCDを何十枚も買って、毎日曲を聴いて、ライブに行って、俺の生活はすっかり潤いを取り戻した。ただ、あの時と違うのは、レン君とは実際に話す機会があることだ。会社でそれとなく金を動かし、レン君が出る番組に集中的にCMを出した。何なら自社商品のCMにも神宮寺レンを起用した。レン君は見事期待に応えてくれて、業績は大幅に上がり、俺は社内でますます地位を高めた。その立場を活かして何度もレン君に会った。打ち合わせや見学、懇親会、パーティ、使えるものは何でも使った。少しでもレン君の姿を見られるだけで俺は本当に幸せだった。
なのに、レン君は俺を裏切った。
「――さんがオレを気に入ってくれるのは嬉しいよ」
「ありがとう。レン君のおかげで俺は生きていられるんだ」
グラスを傾ける綺麗な横顔を見ながら、俺は右腕をそっとレン君の左腕に当てていた。少し高い体温が伝わってくるだけで幸せだった。
二人きりで、と約束して俺は仕事終わりのレン君をバーに連れ出していた。もちろん貸し切りだ。既に何度もこういうことはしていたから、レン君も楽しんでいるんだと思っていた。なのに、この時のレン君は少し距離を離した。
「今度はみんなで遊びに行かないかい? 数が多い方が楽しいよ」
「嫌だよ。他の連中なんかどうでもいい」
「そんな言い方……」
その時の僕はかなり酔っていて、なんだかよそよそしいレン君の態度に苛ついた。
「レン君が一番なんだ。君が最高なんだ。分かるだろ。本当に綺麗で、優しくて……そっくりだ…………」
強引に肩を抱くと、甘い香水の香りが髪から漂った。さらさらの髪が俺の頬を撫でる。あの青い瞳が間近に見えた。誰よりも好きな人と同じだった。
「やめろよ。少し酔い過ぎてるんじゃない」
なのにレン君はすぐに俺の腕を振りほどいた。嫌そうに俺を見下しながら、蓮華ちゃんと同じ瞳で、俺を睨みつけている。意味が分からなかった。
「あんまりふざけるなよ。所詮アイドルの分際で。ヘラヘラ奉仕するのが仕事だろうが!」
カッとなって思ってもいないことを言ってしまったけど止められなかった。でもレン君はレン君で俺の一言がかなり癪に障ったみたいだった。
「今日はもうお互い帰った方がいい。タクシー呼ぶから」
レン君が携帯を手に取った瞬間、俺はすぐにそれを叩き落とした。
「何仕切ってんだお前。状況分かってんのかよ。スポンサー怒らせてんだよ、なぁ!」
「ちょっと……!」
レン君の腕を強く掴むと、俺は耳元で怒鳴りつけた。背はレン君の方がずっと高いけど、体重だったら俺の方が重い。のしかかるみたいにして押さえ込むのは意外と簡単だった。
この時はもうレン君もなりふり構わないで、やめろって何度も言ってたけど、顔が綺麗過ぎて何も怖くなかった。蓮華ちゃんの面影ばかりが俺の目の前にチラついて、ただただ苦しかった。
「スポンサー降りてもいいんだよ。いきなりお金が無くなってニュースになるかもしれないけど、レン君は責任取れんの? そりゃまあ事務所にも実家にもお金は沢山あるだろうけどさぁ、大スポンサー逃がしたアイドルって評判が業界内で付いて回ったらレン君だって困るよね。イメージ商売のアイドルなんだから評判はお金より大事って分かるだろ?」
「それは……っ」
「困るのはレン君だけじゃないよ。そういうアイドルがいる事務所って俺はあちこちに触れ回ってやる。レン君のお友達だって困るんじゃないのかな? おい、どうなんだよ。そこまで分かってて言ってんのか?」
「…………悪かったよ」
レン君は押さえ込まれたまま、目を逸らして謝ってくれた。でもそんな不満そうな態度で俺が満足出来るわけない。レン君は俺を裏切ったんだ。蓮華ちゃんの目で、顔で、俺を裏切ったんだ。俺がどれだけ傷ついたのか、レン君に分かる筈が無い。どれだけ罪深いことをしたのか教えてあげるしかなかった。
「黙って着いてこい。分かってるな」
「…………」
レン君が静かに頷いたのを見て俺はすぐに電話して私用のタクシーを呼ぶと、レン君の腕を掴んだままそれに乗り込んだ。運転手はレン君の顔を見て少し驚いていたけど、俺が住所を言うとすぐに移動してくれた。
着いた先は高級ホテルだった。
「待って。何を勘違いしているのか知らないけど」
「黙って着いてこいって言ったろうが。顔と頭の良さが比例しないのか?」
そう怒鳴りつけると、レン君はまた静かになった。その顔からは明らかに血の気が引いていて、少し可哀想になった。怯えているんだ。俺だってこんなことしたくはなかった。たまにレン君とお酒を飲んで、蓮華ちゃんのことを思い出せる時間があればそれで良かったのに。レン君がこうさせたんだ。そう思うとまた腹が立ってきた。こいつはどうして被害者面をしているんだろう。
チェックインをしてスイートルームを取ると、そのまま直通のエレベーターに乗り込んだ。一緒にお酒を飲んでいるだけの時は遠慮していたけど、もう気を遣う必要もないから、レン君の顔をずっと覗き込んでいた。長い睫も、通った鼻筋も、綺麗な瞳も、さらさらの髪も、何もかも生き写しだった。僕の好きな人がそこにいた。十数年の時を経て、僕は神宮寺蓮華を抱く。そう思うだけで心臓が跳ねた。
「レン君はそっちの経験ある?」
「ある訳ないだろ……」
「へぇ、女遊びはしてるのにね。僕も無いんだ。二人で初めてのセックス楽しもうね」
その時、ちょうどエレベーターが部屋に到着した。すぐにドアを開けてレン君のコートを強引に引っ張って脱がせた。ただでさえスレンダーなシルエットのレン君がますます細く見えて、たまらなかった。男の躰をしていることなんてどうでも良かった。レン君は誰よりも綺麗な人に似ているのだから、興奮出来ない訳がなかった。
「ねぇ、本当に悪かった。謝るよ。だからこれ以上は……」
「ホテルに連れ込まれておいてそんな御託は許されないだろ!」
ベッドに押し倒すと、レン君は小さく呻いた。白いシーツに明るい色の髪が散って綺麗だ。たまらずのし掛かると、レン君の甘い香りがさっき以上に広がる。レン君の躰、レン君の存在全部が僕を満たしている気がした。もう酒の酔いなんてどうでも良かった。僕と好きな人が繋がるって事実だけがあった。
シャツに手を入れるとすべすべの肌の感触が広がる。首筋に顔を埋めながら、くすぐるように触ってあげると、レン君はすっかり身を固くしていた。本当に怖いんだろう。でも言うことを聞かないともっと怖いことになるのもレン君は分かっている。レン君が優しくて良い子で本当に良かった。暴力を振るったりするのは僕の趣味じゃなかった。
「大丈夫、大丈夫。レン君は肌も綺麗なんだね……。可愛いね、ずっと好きだったよ」
「やめっ……やめろよ……」
脇腹を撫でると、レン君は小さく声を洩らした。レン君がくすぐったがりなのは一部の界隈で有名な話だった。その敏感さは事実だったみたいで、俺が耳に息を吹きかけたり、腰を撫でたりするだけでレン君は呻き続けていた。一応声は我慢しているつもりらしくて、唇をぎゅっと噛んでいたけど、もう頬は赤くてすごく性的だった。
「レン君本当に初めてなの? 俺みたいな素人の愛撫で気持ちよくなるなんて随分可愛いね」
「気持ちいい、訳じゃっ……ん……は……ぁ」
「服の上から触るのもアレだし、そろそろ脱ごうか」
「……嫌だ、っあ」
「すごく……綺麗だよ」
レン君のシャツのボタンを外してあげて、ベルトを引き抜いてあげて、その度にレン君は嫌がるそぶりを見せていたけど、少し可愛がってあげるだけで簡単に押さえ込めた。格好いいレン様ってキャーキャー言われているギャップに笑ってしまった。でも仕方がないことなのかもしれない。レン君は蓮華ちゃんにそっくりなんだ。実質女の子みたいなものだ。
そうやって服を脱がせたレン君の躰はすごく性的だった。ピンナップとかで散々見ていた筈なのに、こうしてベッドの上で見ると迫力が違った。汗に塗れて、息をする度に胸が上下して、長い手足は力なく投げ出されている。この躰は僕の為に全部捧げられている。
「レン君、やっぱり気持ちよかったんだね」
「……違う」
普段の自信満々な姿からは信じられないような声で、レン君は答えていたけど、僕の目の前の光景が答えだった。体格に見合った陰茎はしっかり反応を見せていて、大きく勃ち上がっていた。すべすべの亀頭を舌で舐めてあげると、しょっぱい味がした。これがレン君の味なんだ。きっとこの味も蓮華ちゃんに似ているのかもしれない。そう思うともっと舐めていたくて、実際に味わい続けた。尿道口を何度も行き来するだけで先走りの汁は溢れてきて、レン君は大声をあげて喘いでいた。暴れようとする脚を腿から抱えて俺はレン君を味わい続けた。少し時間が掛かったけど、苦い汁が僕の口内を満たしていった。
「嘘だろ……どうして……こんな…………」
掠れた声で呻いているレン君の顔を見ながら、僕はレン君の精液を舌の上でゆっくりと転がしていた。苦いけど、どことなく甘くて、それが蓮華ちゃんの歌声を思い返させるような気がした。美味しい。今まで飲んだどんなものよりも美味しかった。
感じてるレン君の顔も本当に綺麗だった。あのレン君が乱れている。髪を顔に貼り付けて、顔を真っ赤にして、綺麗な瞳を潤ませて僕を見ているんだ。本当に似ていると、何度抱いたか分からない感慨が湧き上がって止まらなかった。
「じゃあ次は僕の番だよ」
「えっ、もう終わりじゃないのかい」
「当たり前だろ。アイドルは奉仕するのが仕事ってさっき言ったのもう忘れたの?」
「それは……そうだけど……」
「じゃあいいよね」
「ちょっと、そこは!?」
咄嗟に身を起こそうとするレン君を無視して、俺はレン君の下半身に手を這わせた。きゅっと締まった太股を辿って、強引に尻を開くと慎ましい孔がそこにあった。確かにレン君の言う通り明らかに経験のない綺麗な場所だ。
「オレも口でしてもいいからっ……本当にやめでっ!?」
「おっ、案外あっさり入るじゃん」
ローションを掛けた人差し指を押し込むと、レン君はすぐに黙ってしまった。愛撫されても濡れない場所だし、初めてだから本当にキツいんだろう。でももう僕はレン君と一つになることしか考えられなかった。
「う゛ぐっ……い゛っ……あ……ん゛んっ…………」
「痛いね、苦しいね。レン君。ごめんね」
元気だったレン君の陰茎もすっかり萎れてしまって、俺が指を増やす度にぶらぶら揺れている。その様子もなんだか可愛く見えてしまうのは惚れた弱みだろうか。本格的にレン君を雌にしてやった気がして、優越感と興奮で頭がおかしくなりそうだった。
「いやっ……だか、ら…………やめ゛て……」
とうとうレン君は顔を手で覆ってしまって、弱々しく呟いた。俺と向かい合っていた時の堂々とした振る舞いなんて微塵も無い。こんな神宮寺レンの姿なんて誰も見たことがないだろう。僕だけのレン君の姿なんだ。そう思うともう我慢出来なかった。
チャックを降ろして自分の陰茎を出すと、既にガチガチになっている。指を引き抜いて先端を押しつけると、レン君は顔色を変えて起き上がった。
「ねぇ、もう逆らったりしない! だからそれだけは……ぁあ゛ああっ!」
「うおっ、締まる……っ!」
まだ其処は狭くて、先を押し込むだけで精一杯だったけど、それで十分だった。信じられないほどの熱さが俺を包んでいた。
「ほら、首に腕回せ。キスしろ」
「……っ」
レン君はもう泣きそうな顔をしていたけど、健気に俺の言うことを聞いてくれた。あのしなやかな腕が俺を抱いて、柔らかな唇が俺に触れた。強く吸い付いて唾液を流し込んだ。レン君は反射的に身を引こうとしていたけど、頭を強く押さえて逃がさなかった。俺をレン君の体液は一つに混じり合って、彼の首筋をだらだら流れた。何度もキスする度に腰を押しつけたらキツキツの中身はもっと締まって、蕩けるように気持ちが良い。
俺はこんなに気持ちが良いのに、レン君の陰茎は萎えたままで申し訳なかったけどそれよりも目の前にある綺麗な顔と極上の感触で俺は夢中だった。そのまま腰を動かすと、レン君は俺の目の前で叫んだ。
「嫌だっ! ああっあ゛っやだっ、やだから……ん゛んっ!」
「ごめんね。ちょっとでも楽になるようにおちんちんいっぱいいじって、キスもたくさんしてあげるからね」
「ぎっ……いい゛いぃい゛いいっ! あ゛っ、だめだ……!」
もう一回イかせたからレン君の気持ちが良いところは少し分かる。孔に強引に押し込みながら陰茎をしごいてあげると、レン君は悲鳴を上げて俺に強く抱きついた。嫌だ、とか止めて、とかそんな懇願が途切れ途切れに聞こえたけど、それに従えるほど俺は優しくなかった。全部入った時には、俺もレン君も汗だくで、辺りには少しの血の臭いと、レン君の甘い香りで満ちあふれていた。俺は手を止めてレン君を眺めた。綺麗な顔が俺を見ている。
泣かせてしまった、と咄嗟に思った。誰よりも大切な人だったのに、それを俺はこんなに傷つけてしまった。でも背徳感以上に達成感が俺を満たしていた。
「やっと報われた……全部、全部この日の為だった。俺が蓮華ちゃんに救われたのも、仕事を頑張ってきたことも、レン君が誰よりも素敵なアイドルになったことも。全部俺達が結ばれる為だったんだよ。ありがとう、レン君」
「違う……違うだろ……」
「違わないよ! ありがとう。愛してるよ」
欲望のままに俺はレン君を犯した。人生でこれ以上無いほど気持ちよかった。ゴムなんて持っていないからレン君のお腹に何度も種を吐き出した。きっと俺と、蓮華ちゃんと、レン君の子供が出来る。きっと会える。誰よりも愛そう。
「…………あ゛……はっ……」
「僕は愛せるよ……、この愛を蓮華ちゃんとレン君が教えてくれたから……」
レン君は僕の言葉には答えずに横になったままだった。孔からは僕の精液が垂れ流されている。髪も乱れて、酷い有様だった。でも僕にとっては誰よりも綺麗に見えた。畳む
蓮華ちゃんはこの世の奇跡だった。
あれはまだ俺が社会に出たばかりの時だった。当時、今でいうブラック企業でこき使われていた俺は、生きる希望を失っていた。
もう死のう。営業回りで怒鳴りつけられた帰り道で、俺は薄暗い決意をした。その時だった。街頭テレビから歌声が降り注いだのは。映っていたのはまだ売り出し中だった神宮寺蓮華だった。
圧倒的な技術と美しい声で紡がれる歌は、俺を此処ではない楽園へと連れて行った。目を引いて離さない美貌とオーラも堪らなかった。霞む視界の中で、食い入るようにテレビを見つめていた。
それから俺は蓮華ちゃんと虜になった。CDを買って毎日曲を聴いて、ライブに行って、彼女に勇気づけられたから俺は仕事にも打ち込むことが出来た。蓮華ちゃんは俺の恩人だった。
だから頑張って耐えた。毎日の理不尽な仕事にも、蓮華ちゃんが明らかに金目当ての年の差婚をしても、彼女が引退してしまっても。俺はずっと蓮華ちゃんを忘れずにいた。彼女が存在しているだけでこの世界を俺は愛おしいと思えた。
それでも、いや、だからこそ蓮華ちゃんがこの世から消えてしまうことには耐えられなかった。
その報道を聞いた時、世界が終わったと思った。その時、俺は会社でもある程度の地位に上り詰めていたが、そんなことはどうでも良くなった。蓮華ちゃんがいない世界に意味はない。後はもうくだらない消化試合だ。抜け殻になった俺は十数年を無為に過ごした。蓮華ちゃん以上に愛せる存在も見当たらなくて、結婚もしていない。家族や親戚なんかもとうに死んだ。これから寿命が尽きるまで生き続けるのだと思うと耐えがたかった。
もう死のう。仕事をしながらそう決意した日、俺は会社がスポンサーをやっている関係で番組制作の内見があった。蓮華ちゃんが生きていた世界を覗けるかもしれない。人生最後の仕事にはふさわしい。そう思って俺は現場に出かけた。
見学する番組は話題の歌手が生放送で歌ってトークをするのが売りの音楽ショーだった。
蓮華ちゃんが亡くなってからテレビなんて一切見なかったから、そこにいる芸能人を俺は誰一人知らなかった。女性アイドルグループが金切り声で歌うのを聞きながら、俺は少し憂いを含んだ蓮華ちゃんの歌声を思い出していた。やっぱりもう蓮華ちゃんはいないんだ。そう思わされるのが辛かった。
もう結構です、そう言って切り上げようとしたその時、ステージに立った人がいた。
彼女そっくりの明るい髪が揺れて、真っ青な瞳が俺を映した。蓮華ちゃん――そう叫びかけて、違うと気づいた。
すらりと高い背、低い声、ステージにいるのは男だった。俺が動揺している間に、前奏が流れて彼は歌い始めた。その歌声ではっきりと分かった。圧倒的な技術と誰もが目を離せないオーラ、同じだった。性別は違っても蓮華ちゃんはまた俺を救いに来てくれたんだ。
そう思えて涙が止まらなかった。会場の大歓声から神宮寺レンって聞こえてくる。
蓮華ちゃんの息子だと知ったのはその後だった。蓮華ちゃんはまだレン君の中で生きているんだ。そしてあの時みたいに俺を救いに来てくれたんだ。俺は確信を持ってその事実を噛みしめていた。
番組への予算を増やすから、レン君と話したい。そうスタッフに声を掛けるとすぐにお膳立てしてもらえた。俺が偉いからこういうことも言える。仕事に打ち込み続けたことが無駄じゃなかったって初めて思えた。
レン君と取る夕食は夢のようだった。俺は全く知らなかったけど、レン君はかなりの売れっ子らしい。今日の収録の裏話や、音楽へのこだわりを軽快に喋ってくれてとても楽しかったし、なにより見れば見るほど蓮華ちゃんに似ていた。雰囲気もそうだし、歌い方も、華やかさも、なにもかも生き写しだった。
それからは全く同じだった。レン君のCDを何十枚も買って、毎日曲を聴いて、ライブに行って、俺の生活はすっかり潤いを取り戻した。ただ、あの時と違うのは、レン君とは実際に話す機会があることだ。会社でそれとなく金を動かし、レン君が出る番組に集中的にCMを出した。何なら自社商品のCMにも神宮寺レンを起用した。レン君は見事期待に応えてくれて、業績は大幅に上がり、俺は社内でますます地位を高めた。その立場を活かして何度もレン君に会った。打ち合わせや見学、懇親会、パーティ、使えるものは何でも使った。少しでもレン君の姿を見られるだけで俺は本当に幸せだった。
なのに、レン君は俺を裏切った。
「――さんがオレを気に入ってくれるのは嬉しいよ」
「ありがとう。レン君のおかげで俺は生きていられるんだ」
グラスを傾ける綺麗な横顔を見ながら、俺は右腕をそっとレン君の左腕に当てていた。少し高い体温が伝わってくるだけで幸せだった。
二人きりで、と約束して俺は仕事終わりのレン君をバーに連れ出していた。もちろん貸し切りだ。既に何度もこういうことはしていたから、レン君も楽しんでいるんだと思っていた。なのに、この時のレン君は少し距離を離した。
「今度はみんなで遊びに行かないかい? 数が多い方が楽しいよ」
「嫌だよ。他の連中なんかどうでもいい」
「そんな言い方……」
その時の僕はかなり酔っていて、なんだかよそよそしいレン君の態度に苛ついた。
「レン君が一番なんだ。君が最高なんだ。分かるだろ。本当に綺麗で、優しくて……そっくりだ…………」
強引に肩を抱くと、甘い香水の香りが髪から漂った。さらさらの髪が俺の頬を撫でる。あの青い瞳が間近に見えた。誰よりも好きな人と同じだった。
「やめろよ。少し酔い過ぎてるんじゃない」
なのにレン君はすぐに俺の腕を振りほどいた。嫌そうに俺を見下しながら、蓮華ちゃんと同じ瞳で、俺を睨みつけている。意味が分からなかった。
「あんまりふざけるなよ。所詮アイドルの分際で。ヘラヘラ奉仕するのが仕事だろうが!」
カッとなって思ってもいないことを言ってしまったけど止められなかった。でもレン君はレン君で俺の一言がかなり癪に障ったみたいだった。
「今日はもうお互い帰った方がいい。タクシー呼ぶから」
レン君が携帯を手に取った瞬間、俺はすぐにそれを叩き落とした。
「何仕切ってんだお前。状況分かってんのかよ。スポンサー怒らせてんだよ、なぁ!」
「ちょっと……!」
レン君の腕を強く掴むと、俺は耳元で怒鳴りつけた。背はレン君の方がずっと高いけど、体重だったら俺の方が重い。のしかかるみたいにして押さえ込むのは意外と簡単だった。
この時はもうレン君もなりふり構わないで、やめろって何度も言ってたけど、顔が綺麗過ぎて何も怖くなかった。蓮華ちゃんの面影ばかりが俺の目の前にチラついて、ただただ苦しかった。
「スポンサー降りてもいいんだよ。いきなりお金が無くなってニュースになるかもしれないけど、レン君は責任取れんの? そりゃまあ事務所にも実家にもお金は沢山あるだろうけどさぁ、大スポンサー逃がしたアイドルって評判が業界内で付いて回ったらレン君だって困るよね。イメージ商売のアイドルなんだから評判はお金より大事って分かるだろ?」
「それは……っ」
「困るのはレン君だけじゃないよ。そういうアイドルがいる事務所って俺はあちこちに触れ回ってやる。レン君のお友達だって困るんじゃないのかな? おい、どうなんだよ。そこまで分かってて言ってんのか?」
「…………悪かったよ」
レン君は押さえ込まれたまま、目を逸らして謝ってくれた。でもそんな不満そうな態度で俺が満足出来るわけない。レン君は俺を裏切ったんだ。蓮華ちゃんの目で、顔で、俺を裏切ったんだ。俺がどれだけ傷ついたのか、レン君に分かる筈が無い。どれだけ罪深いことをしたのか教えてあげるしかなかった。
「黙って着いてこい。分かってるな」
「…………」
レン君が静かに頷いたのを見て俺はすぐに電話して私用のタクシーを呼ぶと、レン君の腕を掴んだままそれに乗り込んだ。運転手はレン君の顔を見て少し驚いていたけど、俺が住所を言うとすぐに移動してくれた。
着いた先は高級ホテルだった。
「待って。何を勘違いしているのか知らないけど」
「黙って着いてこいって言ったろうが。顔と頭の良さが比例しないのか?」
そう怒鳴りつけると、レン君はまた静かになった。その顔からは明らかに血の気が引いていて、少し可哀想になった。怯えているんだ。俺だってこんなことしたくはなかった。たまにレン君とお酒を飲んで、蓮華ちゃんのことを思い出せる時間があればそれで良かったのに。レン君がこうさせたんだ。そう思うとまた腹が立ってきた。こいつはどうして被害者面をしているんだろう。
チェックインをしてスイートルームを取ると、そのまま直通のエレベーターに乗り込んだ。一緒にお酒を飲んでいるだけの時は遠慮していたけど、もう気を遣う必要もないから、レン君の顔をずっと覗き込んでいた。長い睫も、通った鼻筋も、綺麗な瞳も、さらさらの髪も、何もかも生き写しだった。僕の好きな人がそこにいた。十数年の時を経て、僕は神宮寺蓮華を抱く。そう思うだけで心臓が跳ねた。
「レン君はそっちの経験ある?」
「ある訳ないだろ……」
「へぇ、女遊びはしてるのにね。僕も無いんだ。二人で初めてのセックス楽しもうね」
その時、ちょうどエレベーターが部屋に到着した。すぐにドアを開けてレン君のコートを強引に引っ張って脱がせた。ただでさえスレンダーなシルエットのレン君がますます細く見えて、たまらなかった。男の躰をしていることなんてどうでも良かった。レン君は誰よりも綺麗な人に似ているのだから、興奮出来ない訳がなかった。
「ねぇ、本当に悪かった。謝るよ。だからこれ以上は……」
「ホテルに連れ込まれておいてそんな御託は許されないだろ!」
ベッドに押し倒すと、レン君は小さく呻いた。白いシーツに明るい色の髪が散って綺麗だ。たまらずのし掛かると、レン君の甘い香りがさっき以上に広がる。レン君の躰、レン君の存在全部が僕を満たしている気がした。もう酒の酔いなんてどうでも良かった。僕と好きな人が繋がるって事実だけがあった。
シャツに手を入れるとすべすべの肌の感触が広がる。首筋に顔を埋めながら、くすぐるように触ってあげると、レン君はすっかり身を固くしていた。本当に怖いんだろう。でも言うことを聞かないともっと怖いことになるのもレン君は分かっている。レン君が優しくて良い子で本当に良かった。暴力を振るったりするのは僕の趣味じゃなかった。
「大丈夫、大丈夫。レン君は肌も綺麗なんだね……。可愛いね、ずっと好きだったよ」
「やめっ……やめろよ……」
脇腹を撫でると、レン君は小さく声を洩らした。レン君がくすぐったがりなのは一部の界隈で有名な話だった。その敏感さは事実だったみたいで、俺が耳に息を吹きかけたり、腰を撫でたりするだけでレン君は呻き続けていた。一応声は我慢しているつもりらしくて、唇をぎゅっと噛んでいたけど、もう頬は赤くてすごく性的だった。
「レン君本当に初めてなの? 俺みたいな素人の愛撫で気持ちよくなるなんて随分可愛いね」
「気持ちいい、訳じゃっ……ん……は……ぁ」
「服の上から触るのもアレだし、そろそろ脱ごうか」
「……嫌だ、っあ」
「すごく……綺麗だよ」
レン君のシャツのボタンを外してあげて、ベルトを引き抜いてあげて、その度にレン君は嫌がるそぶりを見せていたけど、少し可愛がってあげるだけで簡単に押さえ込めた。格好いいレン様ってキャーキャー言われているギャップに笑ってしまった。でも仕方がないことなのかもしれない。レン君は蓮華ちゃんにそっくりなんだ。実質女の子みたいなものだ。
そうやって服を脱がせたレン君の躰はすごく性的だった。ピンナップとかで散々見ていた筈なのに、こうしてベッドの上で見ると迫力が違った。汗に塗れて、息をする度に胸が上下して、長い手足は力なく投げ出されている。この躰は僕の為に全部捧げられている。
「レン君、やっぱり気持ちよかったんだね」
「……違う」
普段の自信満々な姿からは信じられないような声で、レン君は答えていたけど、僕の目の前の光景が答えだった。体格に見合った陰茎はしっかり反応を見せていて、大きく勃ち上がっていた。すべすべの亀頭を舌で舐めてあげると、しょっぱい味がした。これがレン君の味なんだ。きっとこの味も蓮華ちゃんに似ているのかもしれない。そう思うともっと舐めていたくて、実際に味わい続けた。尿道口を何度も行き来するだけで先走りの汁は溢れてきて、レン君は大声をあげて喘いでいた。暴れようとする脚を腿から抱えて俺はレン君を味わい続けた。少し時間が掛かったけど、苦い汁が僕の口内を満たしていった。
「嘘だろ……どうして……こんな…………」
掠れた声で呻いているレン君の顔を見ながら、僕はレン君の精液を舌の上でゆっくりと転がしていた。苦いけど、どことなく甘くて、それが蓮華ちゃんの歌声を思い返させるような気がした。美味しい。今まで飲んだどんなものよりも美味しかった。
感じてるレン君の顔も本当に綺麗だった。あのレン君が乱れている。髪を顔に貼り付けて、顔を真っ赤にして、綺麗な瞳を潤ませて僕を見ているんだ。本当に似ていると、何度抱いたか分からない感慨が湧き上がって止まらなかった。
「じゃあ次は僕の番だよ」
「えっ、もう終わりじゃないのかい」
「当たり前だろ。アイドルは奉仕するのが仕事ってさっき言ったのもう忘れたの?」
「それは……そうだけど……」
「じゃあいいよね」
「ちょっと、そこは!?」
咄嗟に身を起こそうとするレン君を無視して、俺はレン君の下半身に手を這わせた。きゅっと締まった太股を辿って、強引に尻を開くと慎ましい孔がそこにあった。確かにレン君の言う通り明らかに経験のない綺麗な場所だ。
「オレも口でしてもいいからっ……本当にやめでっ!?」
「おっ、案外あっさり入るじゃん」
ローションを掛けた人差し指を押し込むと、レン君はすぐに黙ってしまった。愛撫されても濡れない場所だし、初めてだから本当にキツいんだろう。でももう僕はレン君と一つになることしか考えられなかった。
「う゛ぐっ……い゛っ……あ……ん゛んっ…………」
「痛いね、苦しいね。レン君。ごめんね」
元気だったレン君の陰茎もすっかり萎れてしまって、俺が指を増やす度にぶらぶら揺れている。その様子もなんだか可愛く見えてしまうのは惚れた弱みだろうか。本格的にレン君を雌にしてやった気がして、優越感と興奮で頭がおかしくなりそうだった。
「いやっ……だか、ら…………やめ゛て……」
とうとうレン君は顔を手で覆ってしまって、弱々しく呟いた。俺と向かい合っていた時の堂々とした振る舞いなんて微塵も無い。こんな神宮寺レンの姿なんて誰も見たことがないだろう。僕だけのレン君の姿なんだ。そう思うともう我慢出来なかった。
チャックを降ろして自分の陰茎を出すと、既にガチガチになっている。指を引き抜いて先端を押しつけると、レン君は顔色を変えて起き上がった。
「ねぇ、もう逆らったりしない! だからそれだけは……ぁあ゛ああっ!」
「うおっ、締まる……っ!」
まだ其処は狭くて、先を押し込むだけで精一杯だったけど、それで十分だった。信じられないほどの熱さが俺を包んでいた。
「ほら、首に腕回せ。キスしろ」
「……っ」
レン君はもう泣きそうな顔をしていたけど、健気に俺の言うことを聞いてくれた。あのしなやかな腕が俺を抱いて、柔らかな唇が俺に触れた。強く吸い付いて唾液を流し込んだ。レン君は反射的に身を引こうとしていたけど、頭を強く押さえて逃がさなかった。俺をレン君の体液は一つに混じり合って、彼の首筋をだらだら流れた。何度もキスする度に腰を押しつけたらキツキツの中身はもっと締まって、蕩けるように気持ちが良い。
俺はこんなに気持ちが良いのに、レン君の陰茎は萎えたままで申し訳なかったけどそれよりも目の前にある綺麗な顔と極上の感触で俺は夢中だった。そのまま腰を動かすと、レン君は俺の目の前で叫んだ。
「嫌だっ! ああっあ゛っやだっ、やだから……ん゛んっ!」
「ごめんね。ちょっとでも楽になるようにおちんちんいっぱいいじって、キスもたくさんしてあげるからね」
「ぎっ……いい゛いぃい゛いいっ! あ゛っ、だめだ……!」
もう一回イかせたからレン君の気持ちが良いところは少し分かる。孔に強引に押し込みながら陰茎をしごいてあげると、レン君は悲鳴を上げて俺に強く抱きついた。嫌だ、とか止めて、とかそんな懇願が途切れ途切れに聞こえたけど、それに従えるほど俺は優しくなかった。全部入った時には、俺もレン君も汗だくで、辺りには少しの血の臭いと、レン君の甘い香りで満ちあふれていた。俺は手を止めてレン君を眺めた。綺麗な顔が俺を見ている。
泣かせてしまった、と咄嗟に思った。誰よりも大切な人だったのに、それを俺はこんなに傷つけてしまった。でも背徳感以上に達成感が俺を満たしていた。
「やっと報われた……全部、全部この日の為だった。俺が蓮華ちゃんに救われたのも、仕事を頑張ってきたことも、レン君が誰よりも素敵なアイドルになったことも。全部俺達が結ばれる為だったんだよ。ありがとう、レン君」
「違う……違うだろ……」
「違わないよ! ありがとう。愛してるよ」
欲望のままに俺はレン君を犯した。人生でこれ以上無いほど気持ちよかった。ゴムなんて持っていないからレン君のお腹に何度も種を吐き出した。きっと俺と、蓮華ちゃんと、レン君の子供が出来る。きっと会える。誰よりも愛そう。
「…………あ゛……はっ……」
「僕は愛せるよ……、この愛を蓮華ちゃんとレン君が教えてくれたから……」
レン君は僕の言葉には答えずに横になったままだった。孔からは僕の精液が垂れ流されている。髪も乱れて、酷い有様だった。でも僕にとっては誰よりも綺麗に見えた。畳む
同居人からプリンに埋もれてるカミュを書いてと言われたので書きました。お題から分かるように悪ふざけのギャグです。パレス組。なんでも許せる人向け。
「これは……?」
扉を開けると、そこには信じられない光景が広がっていました。これでもワタシは魔法の国に生まれた身――突拍子もないものなど山のように見てきましたが、それでも言葉を失ってしまう。
見慣れた生活空間であるワタシの(そして不服ながら同居している彼の)部屋がある筈の場所には、見上げるほどの大きさのプリンがあったのです。何かの間違いかと思って近づいてみるとそれはぷるぷると揺れて、甘い香りを漂わせています。どういう経緯でこのプリンがワタシの部屋に鎮座しているのか知りませんが、原因だけははっきりしていました。
「カミュ!」
怒りに任せて原因の名前を呼びましたが何も返事がない。あの卑しい性根から考えてこのプリンをむさぼっている筈……。
そう考えながら顔を上げると、ワタシはあることに気づきました。プリンの頂点、大量に注がれているカラメルソースで分かりづらかったのですが、そこに見慣れた革靴が突き刺さっていたのです。
プリンの周りをぐるりと歩き回ると、死角になっていたところに梯子が掛けられていました。嫌な予感を抱えながら梯子を登ると、カラメルソースが並々と入ったバケツが梁に置かれ、大量のスプーンが散らばっていました。そして正面に見えるプリンの天辺には、やはり見間違いなどではなく、革靴が突き刺さっているのです。
「Oh……」
前から馬鹿だとは思っていましたが、まさかここまでとは。革靴を掴んで持ち上げると、脚もずるりと付いてきました。気持ちが悪い。最悪です。どれほど前からこんな状態になっていたのか知りませんが、きっともう息はないでしょう。生前あれほど好んでいた甘味に埋もれて死んだのだから、案外恵まれた最後なのかもしれません。プリン葬、ワタシはこの状態をそう名付けました。
「でも絶対に流行らないでしょうね」
あまりにも間抜けすぎます。そろそろ飽きたのでカミュの脚を元のようにプリンに埋めてやり、梯子を降りました。背後から聞き慣れた声が戻れとか貴様も手伝えとか言っているような気がしましたが、ワタシは振り返りませんでした。多分幻聴です。そんなものが聞こえる程度にはワタシも彼を慕っていたようで、部屋の異物よりも寧ろそのことの方に驚いたのでした。
畳む
「これは……?」
扉を開けると、そこには信じられない光景が広がっていました。これでもワタシは魔法の国に生まれた身――突拍子もないものなど山のように見てきましたが、それでも言葉を失ってしまう。
見慣れた生活空間であるワタシの(そして不服ながら同居している彼の)部屋がある筈の場所には、見上げるほどの大きさのプリンがあったのです。何かの間違いかと思って近づいてみるとそれはぷるぷると揺れて、甘い香りを漂わせています。どういう経緯でこのプリンがワタシの部屋に鎮座しているのか知りませんが、原因だけははっきりしていました。
「カミュ!」
怒りに任せて原因の名前を呼びましたが何も返事がない。あの卑しい性根から考えてこのプリンをむさぼっている筈……。
そう考えながら顔を上げると、ワタシはあることに気づきました。プリンの頂点、大量に注がれているカラメルソースで分かりづらかったのですが、そこに見慣れた革靴が突き刺さっていたのです。
プリンの周りをぐるりと歩き回ると、死角になっていたところに梯子が掛けられていました。嫌な予感を抱えながら梯子を登ると、カラメルソースが並々と入ったバケツが梁に置かれ、大量のスプーンが散らばっていました。そして正面に見えるプリンの天辺には、やはり見間違いなどではなく、革靴が突き刺さっているのです。
「Oh……」
前から馬鹿だとは思っていましたが、まさかここまでとは。革靴を掴んで持ち上げると、脚もずるりと付いてきました。気持ちが悪い。最悪です。どれほど前からこんな状態になっていたのか知りませんが、きっともう息はないでしょう。生前あれほど好んでいた甘味に埋もれて死んだのだから、案外恵まれた最後なのかもしれません。プリン葬、ワタシはこの状態をそう名付けました。
「でも絶対に流行らないでしょうね」
あまりにも間抜けすぎます。そろそろ飽きたのでカミュの脚を元のようにプリンに埋めてやり、梯子を降りました。背後から聞き慣れた声が戻れとか貴様も手伝えとか言っているような気がしましたが、ワタシは振り返りませんでした。多分幻聴です。そんなものが聞こえる程度にはワタシも彼を慕っていたようで、部屋の異物よりも寧ろそのことの方に驚いたのでした。
畳む
セシ春書こうとしてプリ春総括みたいになったのでこちらに投稿です。香水コラボの話。
遠くて近いあの頃へ
「あった、あったよ!」
「うわ~全員分ある! 良かった~!」
弾けるような笑い声と一緒に小さな歓声が耳に届いた。話していた内容から、その子達が何を見つけたのかはすぐに分かった。
視線を向けると制服を着て手を繋いだ女の子達が囁き合っているのが見える。彼女たちの前にあるのは予想通り、香水の特設コーナーだった。そこに飾られているのは本当に小さな瓶で、パッケージで微笑んでいるのは今や知らない人がいないほどのアイドル達だった。
女の子達は一本、一本丁寧に香水を手に取ると、一瞬だけ動きを止めて祈るようにそれを見つめた。良かったね、かっこいいねと呟いているのが微かに聞こえてくる。彼女達はそのままレジに向かっていった。まるで踊るように歩く後ろ姿を、わたしは少し眩しい気持ちで眺めていた。
わたしがあまりにも短い学生時代を過ごしたのも、ちょうどあの子達と同じくらいの時だった。あの時はまだ誰も、何者でもなかった。ただの学生として過ごしていても、必死に何者であろうとしていたんじゃないかなと今なら思う。わたしもいろんなコンプレックスを抱えていたし、それはみんな同じだった。ありえない自体の中で偶然垣間見てしまった数々の傷と想いは、当時のわたしの心を大きく揺さぶった。
瞬く間に過ぎ去った日々を思い返しながら、売り場の瓶を手に取る。わたしが使うには少し可愛らしすぎるそれは、手の中で小さく煌めいた。対象年齢を少し上にする案もありました、と企画ついて聞いた時に彼が言っていたことを今更のように思い出した。もうサンプルは家にあったけれどわたしはレジに並んでいた。少し拍子抜けするほど安い値段は、きっと誰でも手が届く。一緒に歩いてくれた数え切れないほど多くの彼女達にも、存在を当たり前のように知ってくれている制服姿の彼女達にも。
早足で家に戻ってから、手首にそっと香りを広げた。むせ返りそうなほど甘い、優しい香りはやっぱり今のわたしには少し可愛らし過ぎる。目を閉じるともっと香りが強まって、目蓋の裏にはたくさんの情景が浮かんだ。ただ一生懸命に音楽と恋を掴もうともがいていたあの頃――今へと続く道を走り始めたわたし達を忘れない為に、そしてこれからも道を歩み続ける多くの人達に寄り添う為に、きっとこの香りはあるのだろう。畳む
遠くて近いあの頃へ
「あった、あったよ!」
「うわ~全員分ある! 良かった~!」
弾けるような笑い声と一緒に小さな歓声が耳に届いた。話していた内容から、その子達が何を見つけたのかはすぐに分かった。
視線を向けると制服を着て手を繋いだ女の子達が囁き合っているのが見える。彼女たちの前にあるのは予想通り、香水の特設コーナーだった。そこに飾られているのは本当に小さな瓶で、パッケージで微笑んでいるのは今や知らない人がいないほどのアイドル達だった。
女の子達は一本、一本丁寧に香水を手に取ると、一瞬だけ動きを止めて祈るようにそれを見つめた。良かったね、かっこいいねと呟いているのが微かに聞こえてくる。彼女達はそのままレジに向かっていった。まるで踊るように歩く後ろ姿を、わたしは少し眩しい気持ちで眺めていた。
わたしがあまりにも短い学生時代を過ごしたのも、ちょうどあの子達と同じくらいの時だった。あの時はまだ誰も、何者でもなかった。ただの学生として過ごしていても、必死に何者であろうとしていたんじゃないかなと今なら思う。わたしもいろんなコンプレックスを抱えていたし、それはみんな同じだった。ありえない自体の中で偶然垣間見てしまった数々の傷と想いは、当時のわたしの心を大きく揺さぶった。
瞬く間に過ぎ去った日々を思い返しながら、売り場の瓶を手に取る。わたしが使うには少し可愛らしすぎるそれは、手の中で小さく煌めいた。対象年齢を少し上にする案もありました、と企画ついて聞いた時に彼が言っていたことを今更のように思い出した。もうサンプルは家にあったけれどわたしはレジに並んでいた。少し拍子抜けするほど安い値段は、きっと誰でも手が届く。一緒に歩いてくれた数え切れないほど多くの彼女達にも、存在を当たり前のように知ってくれている制服姿の彼女達にも。
早足で家に戻ってから、手首にそっと香りを広げた。むせ返りそうなほど甘い、優しい香りはやっぱり今のわたしには少し可愛らし過ぎる。目を閉じるともっと香りが強まって、目蓋の裏にはたくさんの情景が浮かんだ。ただ一生懸命に音楽と恋を掴もうともがいていたあの頃――今へと続く道を走り始めたわたし達を忘れない為に、そしてこれからも道を歩み続ける多くの人達に寄り添う為に、きっとこの香りはあるのだろう。畳む
Powered by てがろぐ Ver 4.7.0.
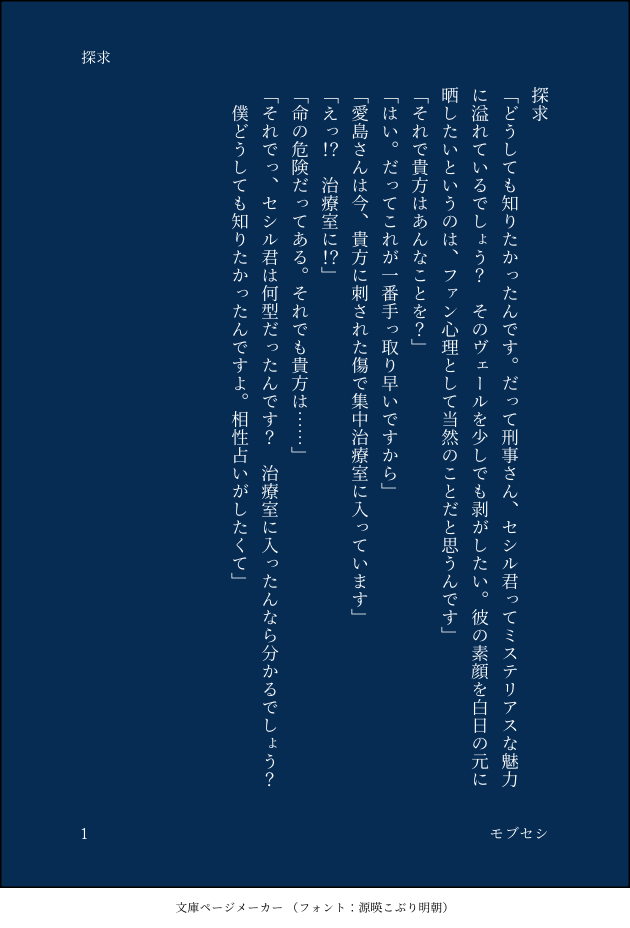
作品はこちらから